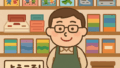※この記事は、過去に執筆した内容を加筆・修正したものです。記載されている内容は当時の状況をもとに整理しています。 ファミコン後期から始まったゲームショップブーム
ファミコン後期に端を発した「ゲームショップブーム」。
業界の主流ハードが変わるたびに、流通も大きな変化を余儀なくされ、ショップはその都度その流れに振り回される状況が続いていました。
スーパーファミコン一強時代とショップの個性
スーパーファミコンが一強だった頃(特に後期)、私もゲームショップ業界に足を踏み入れることになります。
勤務先は任天堂の系列ではありませんでしたが、同様の店舗は周囲にも少なく、それほど大きな問題ではありませんでした。
むしろ印象的だったのは、各店舗ごとに際立った「個性」があったことです。
例えば、セガ好きの店長、ネオジオ好きの店長といった具合に、店の色を全面に出して経営していました。私は「PCエンジン好き店員」として認知され、それぞれの得意分野を活かしながら、仕入れのアドバイスや余剰在庫の融通などを行っていました。
当時は非常に活気があり、働いていて楽しい時期でもありました。もっとも、売上の中心はやはりスーパーファミコンでしたが。
プレイステーションの登場と業界革命
そんな中、業界に大きな転機が訪れます。
それが「プレイステーション」の登場でした。
従来の「おもちゃ流通」から脱却し、メーカーとの直接取引が始まりました。
価格も大きく改定され、1万円を超えることも珍しくなかったソフトが、6000円台で販売されるようになります。
当然ながら、メーカーとの「契約」が必須となり、これまでの慣習とは大きく異なる体制が整えられていきました。
さらに当時大きな話題となったのが「中古禁止」問題です。
ゲームショップにとって中古は生命線でしたが、ソニーは中古販売を認めず、大手チェーンとの間で大きな対立が生まれました。裁判に発展したこともあり、この時期の小売は不安定な状況に置かれていました。
仕入れ・利益率の変化と小売の実情
新品価格が下がる一方で、仕入れの掛率は上昇。
結果として利益率は下がり、ショップには重圧となりました。
ただし、それがどの程度の影響を及ぼしたかは、店舗の規模や形態によって大きく異なります。
少なくとも私の勤めていた店舗では、あまり大きな問題にはなりませんでした。
その理由は「売れる本数が桁外れに増えた」からです。
スーパーファミコン時代には供給制限が厳しく、人気ソフトは十分に仕入れられませんでした。しかし、プレイステーションやセガサターンの時代には、人気作であっても大量入荷・迅速な再販が可能となり、販売機会が大幅に拡大しました。
PS・SS時代の急成長
ファイナルファンタジー、ドラゴンクエストといった国民的タイトルはもちろん、鉄拳やバーチャファイターなどのキラーソフトも次々に登場。
プレイステーションとセガサターンが互いにヒット作を生み出すことで市場は活性化し、当時勤めていたショップも大きく成長しました。
直営店舗数は6店から20店以上に拡大。まさに「イケイケ」の時代であり、新品の安定供給と早い再販は、小売業者だけでなく、メーカーにとっても革命的な仕組みだったといえるでしょう。